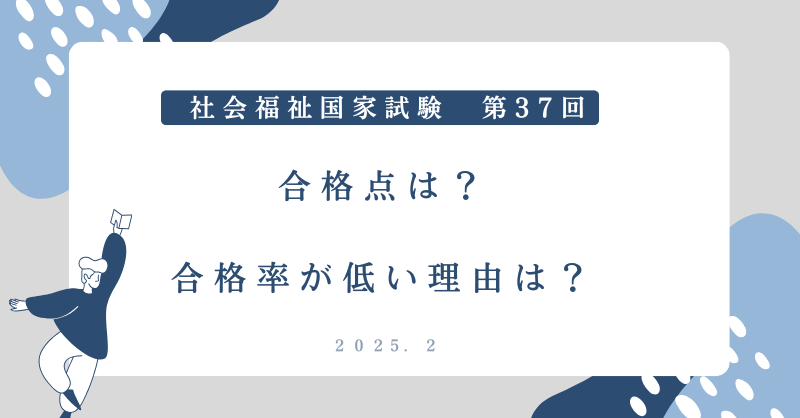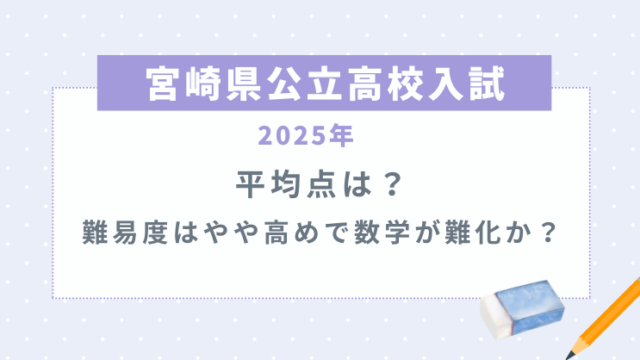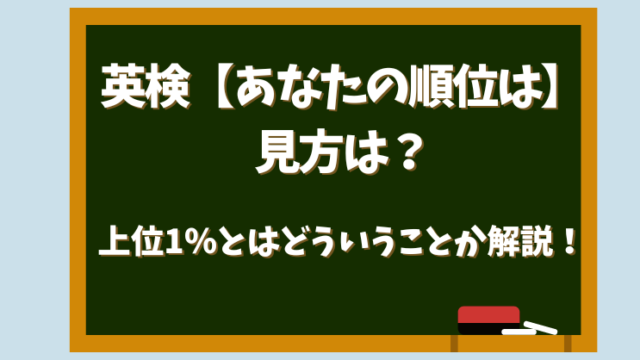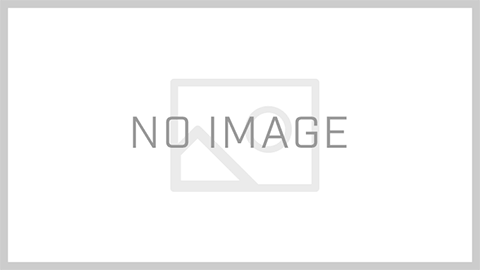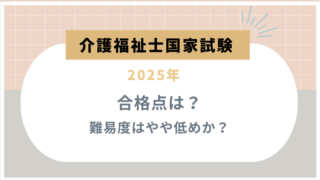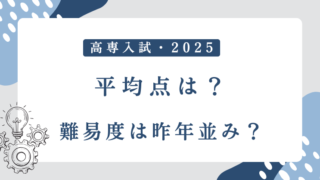社会福祉士国家試験(第37回)の合格点について、気になっている人が多いようですね。
試験を終えて、自己採点をし、自分はボーダーあたりなのかと不安になっている人もいると思います。
そんな社会福祉士国家試験(第37回)の合格点はどのくらいと予想されているのか?
また、合格率は何%程度なのか?なぜ合格率が低いと言われているのか・・・?
この記事では、社会福祉士国家試験(第37回)の合格点、合格率など、気になることをまとめています。
Contents
社会福祉士国家試験2025(第37回)合格点は?
社会福祉士国家試験2025(第37回)の合格点は何点と予想されているのかというと・・・
【合格点予想】78点前後
【合格率予想】40%前後
過去数年間の合格点は90点前後で安定していましたが、2025年に実施された第37回社会福祉士国家試験は、新カリキュラムに基づき、出題数が129問に減少しました。
それに伴い、合格点は78点前後になるのではと予想されています。
ちなみに第36回社会福祉士国家試験の難易度は、前年と比べて大きな変化はありませんでした。
では、過去の会福祉士国家試験合格点、合格率についても、参考までに見ておきましょう。
過去の社会福祉士国家試験の合格点・合格率は?
過去の社会福祉士国家試験合格点は以下の通りです。
| 年/回数 | 合格点 | 合格率 |
| 2024年 / 第36回 | 90点 | 58.1% |
| 2023年 / 第35回 | 90点 | 44.2% |
| 2022年 / 第34回 | 105点 | 31.1% |
| 2021年 / 第33回 | 93点 | 29.3% |
| 2020年 / 第32回 | 88点 | 29.3% |
| 2019年 / 第31回 | 89点 | 29.9% |
2022年に合格点が105点と比較的高い点数になっていますが、それ以外は90点前後という印象です。
2024年の第36回の社会福祉士国家試験については、「やや問題が易しかった」と言われているので、100点前後、100点を超える合格点を予想している人が多くいましたが、結果は例年と変わらず90点が合格点でした。
また、過去5年間の平均合格率は、32.8%です。
合格率は年々上昇傾向にあります。
これまで合格率が低いと言われていた社会福祉士国家試験ですが、2025年も昨年と同水準の合格率になると予想している人が多いです。
社会福祉士国家試験合格点の基準は?
2025年の第37回社会福祉士国家試験では、新カリキュラムの導入により、出題数が129問に変更されました。この試験の合格基準は以下の通りです。
- 得点率60%程度が目安
- 総得点129点中、78点以上が基準となります。ただし、問題の難易度に応じて補正が行われる場合があります。
- 全6科目群で得点が必要
- 試験は6つの科目群に分類されており、各科目群で最低1問以上正解することが条件です。いずれかの科目群で0点の場合、不合格となります。
- 補正の可能性
- 難易度によって基準点が上下することがあります。過去の試験では基準点が60%を下回ることもありましたが、新カリキュラム初年度であることから、今回は基準通りの78点前後になる可能性が高いと考えられます。
新カリキュラムなったことで、出題数が減少したことで、1問あたりの重要性が増しています。
試験内容は「地域共生社会」や「ソーシャルワーク」の視点を重視した新しい出題傾向となっています。
また、精神保健福祉士資格を持っている場合や一部科目免除を受ける場合も、合格基準は変わりません。
ただし、免除対象者には以下のような調整があります。
1. 試験科目免除者の場合
- 配点は45点満点となり、その60%程度(27点以上)が合格基準となります。
2. 精神保健福祉士資格保持者の場合
- 精神保健福祉士試験自体では、総得点132点中60%(約79~80点)が基準ですが、社会福祉士試験を受験する際には通常の基準(129点中78点程度)に従います。
社会福祉士国家試験合格率が低い理由は?
社会福祉士国家試験は、福祉系資格の中でも特に難易度が高いとされ、合格率が低い理由には以下の要因が挙げられます。
1. 出題範囲の広さ
- 試験は19科目(18科目群)にわたり、高齢者福祉、障害者福祉、地域福祉、法律、心理学など多岐にわたる分野から出題されます。
- 全科目群で最低1点以上得点する必要があり、苦手分野を作ることができません。
2. 合格基準の厳しさ
- 合格には総得点の約60%以上を正答する必要があります(2025年試験では129点満点中約78点以上と予想)。
- さらに、全科目群で1問以上正解していることが条件であり、どれか1つでも0点の場合は不合格となります。
3. 試験問題の難易度
- 基礎的な知識だけでなく、応用力や深い理解を必要とする問題も含まれています。
- 新しい制度や社会問題に関する出題も多く、最新の知識を常にアップデートする必要があります。
4. 学習時間の確保が困難
- 社会人受験者が多く、仕事や家庭との両立が求められるため、十分な学習時間を確保することが難しい場合があります。
5. 受験者層の多様性
- 新卒者と既卒者では合格率に大きな差があります。新卒者は比較的高い合格率を示しますが(2024年では76.8%)、既卒者は41.7%と低い傾向があります。
2025年から新カリキュラムが適用された第37回試験では、出題数が129問に減少し、新しい内容への対応が求められます。
出題数減少により1問あたりの重要性が増し、得点率60%を達成するハードルが高くなる可能性があります。
新カリキュラムでは「地域共生社会」や「ソーシャルワーク」の視点を重視した内容となり、新しい分野への対応力が求められます。
合格率の変動
- 2023年(44.2%)および2024年(58.1%)は旧カリキュラム最後の試験であり、例年より合格率が高くなりました。
- 2025年は新カリキュラム初年度となるため、受験者全体で適応に差が生じる可能性があり、合格率は再び低下し30~40%台になる可能性があります。
社会福祉士国家試験は出題範囲の広さや厳しい基準、高い問題難易度などから難関資格とされています。
2025年から新カリキュラムへの移行によって内容や形式が変わり、多くの受験者にとって新たな挑戦となるため、合格率は再び低下する可能性があります。
まとめ
2025年の第37回社会福祉士国家試験では、新カリキュラムの導入により出題数が129問に減少しました。
この変更に伴い、合格点は78点前後、合格率は50~60%程度と予想されています。
過去の試験では、合格点は90点前後で安定しており、合格率も近年は上昇傾向にありました(2024年は58.1%)。
しかし、新カリキュラム初年度である2025年は、出題内容の変化や適応の差から、合格率が再び低下し30~40%台になる可能性も指摘されています。
社会福祉士国家試験が難しい理由として、試験範囲の広さや厳しい合格基準が挙げられます。
試験は19科目(18科目群)から出題され、全科目群で1問以上正解する必要があります。
また、得点率60%以上が基準となり、1問あたりの重要性が増したことで難易度がさらに高まっています。
さらに、新しい制度や社会問題への対応力も求められるため、最新知識の習得が不可欠です。
特に社会人受験者は学習時間を確保しづらく、新卒者と既卒者で合格率に大きな差があります。
新カリキュラムでは「地域共生社会」や「ソーシャルワーク」の視点を重視した内容への対応が必要であり、多くの受験者にとって新たな挑戦となるでしょう。